この記事について
・介護福祉士国家試験に関する用語集
・今までの僕の過去問解説やKindle本で出題されている用語を随時まとめています
・多少の順序のずれはご了承ください。
・普段の記事作成や投稿などのタイミングで随時更新していきます。
* Ctrlキー or ⌘キー+Fキーでの簡易検索もおすすめです。
*最終更新 R.7.7/27
あ〜お
アイコンタクト
目を見て話すことで、関心や安心感、信頼感を相手に伝える視覚的コミュニケーションの技法
ICF(国際生活機能分類)
WHOが提唱した、障害を医学的な側面だけでなく、環境や個人因子との相互作用を含めた全体的な視点で捉える考え方
アイスマッサージ
氷や冷たいもので皮膚を刺激し、感覚を目覚めさせる方法のこと。
愛着障害
他人とのかかわりが難しく、特定の人との親密な人間関係が結べないなどの特徴がある障害
愛着理論
養育者に対する乳児の愛着行動についての理論
あいづち
会話の流れを円滑にし、話をしやすい雰囲気を作るために短く返答する技術。(「はい」「そうですね」「なるほど」「わかります」など。)
アクシデント
過失はあったが、事故にならなかったもの
アクティビティ・ケア
日々の生活が充実できるよう趣味や活動を取り入れる方法のこと
アサーティブコミュニケーション
相手を尊重しながら意見を伝え合うコミュニケーション法
アセスメント(介護過程)
利用者の状況を総合的に把握し、適切な支援につなげるための評価・分析のプロセスのこと。情報収集、情報の分析、ニーズの把握、生活課題の抽出の過程がある。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)
今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス
アドバンスディレクティブ
患者が意識不明や意思表明不能になった際に、医療上の処置や治療を患者自身が意思決定するための文書
アドボカシー
利用者が自らの意思を表明できない場合や、声を届けにくい状況にある際に、その権利や利益を代弁・擁護する行為やプロセス
アパシー
無気力、無関心、意欲低下といった特徴を持つ症状
アルツハイマー型認知症
脳内に異常なたんぱく質(アミロイドβやタウなど)が蓄積し、神経細胞が徐々に壊れていくことで、記憶障害や認知機能の低下が進行する認知症。
アンチエイジング
加齢に抵抗して健康的に生きようとすること。運動や食事、スキンケア、ストレス管理など。
安心安全欲求
マズローの欲求階層説のうち、心身が健康で経済的にも安定した暮らしをしたい欲求
安静時振戦
安静時に手や足が震えること。パーキンソン病4大症状の1つでもある。
言い換え
相手の言葉の意味を変えずに、別の表現で伝え直す技術。(「最近疲れやすくて…」 → 「体調が優れない日が続いているんですね。」)
医学的管理の必要がない爪
爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
育成医療
18歳未満である精神障害児を対象とする自立支援医療
意識混濁
覚醒レベルや周囲の認知能力が低下した状態
意思決定支援
障害者が自らの意思を表明し、それに基づいて行動できるよう支援する考え方。意思形成支援、意思表明支援、意思実現支援の3つの要素がある。
一語文
1歳前後からみられ、「ワンワン」、「ブーブー」など1つの単語から意味を成す文のこと
胃結腸反射
胃が食物を受け入れると、結腸(大腸)への刺激が伝わる反射
医師
診断・治療を通じて利用者の健康管理を担う医療専門職。介護現場での主な役割として、施設の嘱託医など利用者の健康管理や診断・治療を行う。
一包化
同じタイミングに服用する薬を1つの袋にまとめること。
糸賀一雄
「この子らを世の光に」を理念に障害児福祉に尽力し、日本の障害福祉の礎を築いた人物。
意味記憶
一般的な知識や事実の記憶を指す記憶
1回換気量
1回に吸い込める空気量
溢流性尿失禁
男性に多く、少しずつ尿が漏れてしまう、自分で出せないといった尿失禁
移動支援
障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」のひとつで、知的・精神・身体障害のある人が外出時に円滑に移動できるよう支援するサービス
移動用リフト
自力での移動や移乗が困難な人を持ち上げる福祉用具
医療保護入院
精神保健指定医の診察結果に基づき、家族等の同意を得て、本人の同意なしに行われる入院
インクルージョン
個人が持つ能力や価値観などが認められ、それらが活用される社会や組織を目指すこと
インスリン
血糖値を下げる働きを持つホルモン
インテーク
介護福祉職や医療職が利用者やその家族と初めて面談を行い、ニーズや生活状況など必要な情報を収集するプロセス
インフォーマルサービス(私的サービス)
地域住民や家族、ボランティアなど公的な制度以外のサービスや支援のこと。地域住民や家族、ボランティアなどがあてはまる。
インフォームド・コンセント(説明と同意)
介助など何かをするときに、介助に入る前に相手に目的や内容を説明し同意を得ること
ヴィクトール・フランクル
「夜と霧」の著者で、意味を求める生き方(ロゴセラピー)を説いた精神科医
ウェッブ夫妻
ナショナルミニマム(最低生活保障)を提唱
うつ病
脳の働きや神経伝達物質のバランスの乱れなどにより、気分が落ち込む・意欲が出ない・楽しめないといった状態が続く精神疾患の一つ。特徴として、眠れない・食欲がない・集中できない・自分を責めるなどの症状が現れ、日常生活に大きな支障をきたすことがある。
うつ病の3大妄想
貧困妄想、心気妄想、罪業妄想をさす
うなづき
「ちゃんと聞いていますよ」という合図や話を促進する(話しやすい雰囲気を作る)ための技法
運動麻痺
手や足などの筋肉の動きをコントロールしにくくなり、力の調整が難しくなる状態。
運動失調
脊髄小脳変性症で特徴的であり、手足の震えや体のふらつき、発語の不明瞭など、脳からの運動指令がうまく伝わらず、協調運動が障害されるために起こる症状のこと
運動性失語(ブローカ失語)
大脳のブローカ野(左前頭葉)の損傷によって生じる失語症。言葉の理解はできるが、流暢に話せず、短い単語や簡単な表現しか使えないと言った特徴がある。
エイジズム
年齢を理由に偏見や差別をすること。高齢者は頑固だ、・医師が「年だから仕方ない」と言って、痛みや症状を軽視するなど。
HDS-R(改訂 長谷川式簡易知能評価スケール )
記憶・見当識・計算力などを評価し、認知症の疑いを判定するための簡易認知症スクリーニング検査法。
栄養士
食事の管理を行い、栄養バランスを考慮した食事提供を支援する職種。主な役割として、食事管理を担当するが、栄養ケア計画の作成はできない
(管理栄養士の指示のもと業務を行う)。
エコノミークラス症候群
長い時間、足を動かさなかったり、脱水症状によって血栓ができ肺塞栓などの原因ともなる疾患
エコマップ
利用者本人を中心として、利用者の家族や友人、利用者が関わる病院や行政機関等との関係性を視覚的に示したもの
エド・ロバーツ
「できないことは支援を活用しながらも、自分らしく生きることが自立である」とする新しい自立観を提唱した人物
SDS(セルフ・ディベロップメント・サポート)
自分でスキルアップや学習を行うための取り組みを、企業が支援する仕組み
エピソード記憶
陳述記憶の1つであり、経験した出来事に関する記憶のこと
MMSE(精神状態短時間検査)
記憶・計算・言語・注意力・視空間認知など認知機能を総合的に測定し、診断補助や進行度評価に用いられる標準化された認知機能評価尺度。
エンゲル係数
家計の消費支出のうち、食費が占める割合を示す指標のこと。これが高いほど、生活に余裕がない傾向があるといわれている。
炎症性腸疾患
免疫異常によって腸に慢性的な炎症が起こる病気。主に潰瘍性大腸炎やクローン病が含まれる
エンパワメント
その人の持つ力を引き出し、自ら課題を解決できるよう支援すること。
エンパワメントアプローチ
利用者の本来の力を引き出し、問題解決や意思決定の能力を高める支援方法。
応急入院
直ちに入院が必要で、家族の同意が得られない場合に、精神保健指定医の判断で72時間以内に制限して行われる入院
黄色ブドウ球菌
おにぎりやサンドイッチなどによる食中毒や膿瘍などを引き起こし、皮膚や鼻に常在し、傷口や免疫力の低下した人に感染症を引き起こす細菌
応能負担
利用者負担において、その人の所得や負担能力に応じて負担額が決まること
オストメイト
病気やけがなどで人工肛門や人工膀胱を造設し、排泄のためのストーマ(開口部)をもつ人のこと
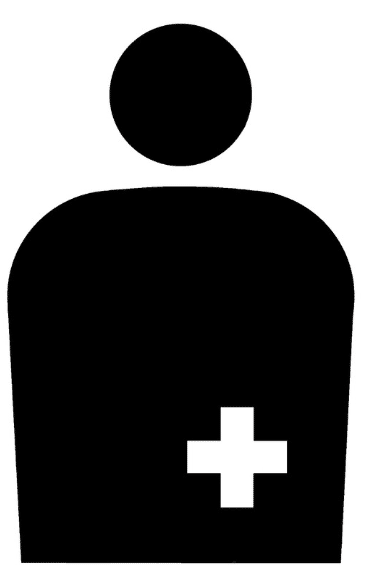
Off-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)
職場外で業務に関連する知識や理論を学ぶ研修やセミナーのこと
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)
実際の現場で、上司や先輩が知識や技術等の指導を行う研修形態
温罨法
身体の特定部位を温めて血流を促すケア方法。
温熱作用
お湯の温度によって生じる効果のこと。血管の拡張によって血行が促進され、新陳代謝や内臓の働きが活発になる効果がある。
か〜こ
カーラー救命曲線
心臓や呼吸の停止、出血などの時間経過と死亡率の関係を表すもの
外因性精神障害
身体的・物質的な外的原因(外傷・感染・薬物など)によって脳が直接的に障害されて起こる精神疾患。脳腫瘍やアルコール依存症、認知症などがある。
介護過程
利用者の望む生活に向けて、客観的で科学的な思考と実践の過程。アセスメント、介護計画の立案、介護の実施、評価の4つのサイクルがあり、利用者の生活の質(QOL)を向上させることが目的である。
外呼吸
肺胞と血液とのガス交換
介護計画(個別介護計画)
利用者の生活課題やニーズに基づき、適切な介護サービスを提供するための計画書。主に、介護福祉職(介護職員・介護福祉士)が作成するが、計画作成担当者(ケアマネジャーや生活相談員)が作ることもある。
介護サービス計画(ケアプラン)
利用者の生活や介護の課題に応じて、全体的な支援の方向性と必要な社会資源の提供方法をまとめた計画書のこと。介護保険施設であれば施設サービス計画、居宅であれば居宅サービス計画という。介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護保険サービスを利用するためのケアプラン(介護サービス計画)を作成し、適切な介護サービスを調整する専門職。ケアプランの作成を中心に、利用者や家族の相談に応じ、サービス事業者との連携や調整、経過の確認とプランの見直し、地域資源の活用支援などを行う。
介護付有料老人ホーム
介護サービスがセットになった有料老人ホーム。施設内に介護職員が常駐しており、食事・入浴・排泄などの日常生活支援や医療的ケアも受けられる。要介護者でも安心して入居できる施設形態。
介護の3原則
「利用者の生活を尊重し、自立を支援する」ための基本的な考え方。「生活の継続性」「自己決定の尊重」「残存能力の活用」の3つの要素がある。
介護の社会化
個々の個人や家族が介護の負担を抱え込むのではなく、社会全体で税や保険料を通じて専門的な介護サービスを確保する考え方
介護福祉士
身体介護・生活支援など、日常生活を直接支援する専門職
介護福祉職の主な役割
主な役割として、日常生活の支援や利用者の状態の観察と情報提供、精神的なサポートと傾聴、他職種との連携、利用者の自立支援などがある
介護保険制度の財源
公費(税金)50%、第1号保険料23%、第2号保険料27%で構成されている。
後期高齢者医療制度の財源
公費約50%、高齢者の保険料約10%、現役世代からの支援金(後期高齢者支援金)約40%で構成されている。
介護予防
できる限り要介護の状態になることを避け、またはその進行を遅らせるための取り組み
介護予防・日常生活支援総合事業
主な事業として、訪問型サービス(第一号訪問事業)、通所型サービス(デイサービス)、介護予防教室、地域包括支援センターがあり、市町村が中心となって、高齢者が自立した生活を維持し、介護が必要になることを予防するための取り組みのこと
介護老人福祉施設
原則、要介護3以上の高齢者が入所できる施設(特別養護老人ホーム・特養)。常時介護が必要で、在宅での生活が困難な高齢者に、生活介護や機能訓練を提供する。
概日リズム睡眠障害
例えば不規則な生活など、人間の体内リズムの周期が地球の24時間サイクルとずれが生じるために睡眠・覚醒のリズムが乱れ、睡眠に障害が生じること
疥癬
ヒゼンダニが原因であり、丘疹や強いかゆみが見られる特徴を持つ皮膚の疾患
咳嗽反射
気道内の異物など分泌物を排出するための反射
海馬
脳の中にある記憶を司る部分で、特に、物事を覚えたり思い出したりするのに重要な働きをもつ。大脳側頭葉の内側部に位置しており、大脳辺縁系の一部でもある。
外発的動機づけ
例えば、「今の歩行はふらつきもなくしっかりと歩かれていますね。すごいですよ。この調子で頑張りましょう」というように周囲の人からの声かけなどを通して、目的とする行動を促す動機づけ
回復期
主に急性期の治療が終わり、患者が日常生活に戻るためのリハビリテーションや機能回復を重点的に行う時期
潰瘍
皮膚や粘膜の表面が傷つき、欠損した状態のこと
下顎呼吸
下顎を上下させ、口をパクパクさせてあえぐような呼吸。死期が近い指標でもある。
画一的
何もかも一様にそろっていて個性や特徴がないさま
核家族
家族の形態について、「夫婦のみ」「夫婦と未婚の子供」「父親または母親とその未婚の子供」の世帯のこと
学習障害
全般的な知的能力には問題がないものの、特定の学習領域において著しい困難を示す発達障害。
学習性無力感
セリグマンが提唱した、自分の行動が結果をもたらさないという経験を何度も繰り返していくことで、何をしても無駄であると考え、自ら行動を起こさなくなる心理状態のこと
過呼吸
不安や緊張等の心理ストレスを感じている時に、浅く呼吸回数が増えること
下垂体
ホルモン分泌を司る内分泌の中枢。成長ホルモン・性ホルモン・甲状腺刺激ホルモンなどの分泌に関与
ガス交換
体内での酸素と二酸化炭素を交換するプロセス
仮性認知症
主にうつ病が原因として、一時的に記憶力や集中力、判断力などの認知機能が低下した状態
家族
介護福祉職にとっては、利用者の生活支援の協働パートナー的な存在であり、利用者にとっては、唯一無二の存在。
片麻痺
脳卒中など、体の左右どちらか一方の手足に麻痺が生じる状態。
家庭裁判所
家庭や親族に関する問題や未成年者の保護、相続、成年後見などの事件を専門的に扱う裁判所
寡動
動作が遅くなったりすること。パーキンソン病4大症状の1つでもある。
神谷美恵子
ハンセン病医療に従事し、『生きがいについて』を通して生きる意味を問い続けた精神科医。
カリブレーション
相手の表情やしぐさを観察し、感情や状態に合わせた柔軟な対応を行う共感的観察技法
カルシウム(Ca)
骨や歯の主成分であると同時に、筋肉の収縮・神経伝達・ホルモン分泌の調整にも重要なミネラル
感覚麻痺
触られた感覚や痛み、温度などの刺激を感じにくくなる状態。
感覚性失語(ウェルニッケ失語)
大脳のウェルニッケ野(左側頭)の損傷によって生じる失語症。スムーズに話せるが、意味が通じにくく、相手の言葉の理解も困難になるといった特長がある。
寛解
症状が治まり穏やかな状態
換気
体外から酸素を取り込み、体外に二酸化炭素を排出する働き
看護師
医療的ケアや健康管理を通じて利用者の生活を支える医療職。主な役割として、利用者の健康管理や医療的ケア(服薬管理、バイタルチェック、処置など)を行う。
肝臓
代謝や中毒性物質の解毒や分解、胆汁の分泌などの働きがある消化器
関節拘縮
関節を動かす機会が減ることで動かせる範囲が小さくなる現象
感情失禁
感情のコントロールが難しくなり、些細なことで突然泣いたり笑ったりする状態。脳血管障害後にみられることが多い。
関節リウマチ
30〜50歳代女性に多く、自己免疫異常によって、免疫系が誤って自分の関節組織を攻撃する慢性的な炎症性性疾患。
感染性腸炎
細菌やウイルスなどの病原体が腸に感染して起こる腸の炎症性疾患
観念運動失行
単純な動作の模倣や指示された動作を適切に実行できない状態(運動機能や理解力には問題がない)。例えば、「指でピースサインを作って」と言われてもできない(意図はあるが動きが再現できない)
観念失行
一連の動作の手順や物の使い方がわからなくなり、動作の順序や目的に沿った行動ができない状態。例えば、「歯ブラシで歯を磨いて」と言われても、歯ブラシを持ったまま口に入れず他の動きをしてしまう(手順が組み立てられない)
管理栄養士
栄養管理の専門家であり、個別の栄養ケア計画を作成し、健康状態に応じた食事提供を行う職種。主な役割として、利用者の栄養ケア・マネジメントを担当し、適切な栄養管理を行う。
記憶
経験した情報を脳に保持し、それを必要に応じて想起する能力のこと。情報を覚える(記銘)→一定時間覚えておく(保持)→思い出す(想起)の3つの過程からなる。
記憶障害
過去の出来事や新しい情報を思い出せなくなる状態。アルツハイマー型認知症で顕著にみられる。
基幹相談支援
地域の障害福祉の中核機関として、困難事例への対応や関係機関との調整などを担う相談支援機関
義肢装具士
医師の指示のもとに装具や義肢の制作をする専門職
器質性便秘
大腸がんや腸閉塞などの構造的な異常が原因で起こる便秘
キットウッド
認知症ケアの1つにあるパーソンセンタードケア(PCC)を提唱する
機能性尿失禁
排泄機能には問題がないが、認知症や身体機能の低下などによって、トイレの場所がわからなかったり、トイレまで間に合わないことで生じる尿漏れのこと
機能性便失禁
認知症や精神的な障害などにより、排便行為そのものは可能であるものの、適切なタイミングや場所での排便が困難になる便失禁
機能性便秘
腸の動きが低下して便の移動が遅くなることで起こる便秘
気分障害
感情や気分の異常が持続し、日常生活に支障をきたす障害のこと
虐待の種類
主な虐待として、身体的虐待、心理的虐待、介護等放棄(ネグレクト)、経済的虐待、性的虐待の5つがある。
逆転移
介護福祉職が利用者に対して自分の感情を向けてしまうこと
逆流性食道炎
胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流し、食道の炎症を起こして胸やけや喉の痛み、悪心などが生じる病気
キャラバンメイト
認知症サポーター研修の講師のこと
球麻痺
脳幹の延髄にある脳神経核が障害されることで、ろれつが回らなくなったり嚥下障害などがみられる麻痺
共感
相手の感情や状況を理解し、寄り添う気持ちを持つこと
共生型サービス
2018年に創設され、障害福祉サービスを提供する事業所が介護保険の指定を受けて実施するサービス形態。訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)がある。
協議会
障害者総合支援法に基づき、地方自治体が設置するものであり、地域における障害者の生活や支援に関する重要な意見交換や協議を行い、支援体制の整備を推進する役割がある機関。情報機能、調整機能、開発機能、教育機能、権利擁護機能、評価機能の6つの機能がある。
共助
地域包括ケアシステムの1つで、介護保険や医療保険など社会保険制度によるサービスのことをいう。
胸腔内
胸骨、肋骨、脊柱、そして横隔膜に囲まれた空間
共同生活援助(グループホーム)
障害福祉サービスの「訓練等給付」に分類されており、障害のある方が他の利用者と共同生活を送りながら、スタッフの支援を受けて日常生活の自立と地域社会での生活を目指す住まいの形態
強度行動障害
知的障害や発達障害(とくに自閉症スペクトラム障害)のある人に見られる、日常生活に著しい支障をきたすような激しい問題行動が持続的に見られる状態
居宅サービス
自宅での生活を継続できるよう、訪問・通所・短期入所などの支援を行うサービス。訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与・特定福祉用具販売などがある。
起立性低血圧
起き上がりや立ち上がり時に、急に血圧が下がり脳血流量が減ることで、めまいや失神が起きること
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
運動神経(運動ニューロン)が障害され、全身の筋力が低下・萎縮していく進行性の神経難病のこと。筋萎縮・筋力低下や嚥下障害、構音障害(発話の困難)などの主症状があり、感覚や認知機能、眼球運動は基本的には保たれている。
緊急措置入院
急速を要し、措置入院の手続きが取れない場合に、精神保健指定医1名の判断で72時間以内に制限して行われる入院
筋固縮
筋肉のこわばりのこと(関節の動きが硬くなる)。パーキンソン病4大症状の1つでもある。
筋ジストロフィー
筋肉の線維が徐々に壊れて筋力が低下し、運動機能など多様な障害が生じる指定難病
筋繊維(線維)
筋肉を構成する基本的な細胞(筋細胞)のこと
グリーフ(悲嘆)
喪失(例:死別、別離など)によって生じる、心理的・行動的・身体的・社会的・スピリチュアルな反応の総体のこと
グリーフワーク
喪失によって生じた悲嘆を受け入れ、乗り越えていく過程のこと。グリーフのプロセス(段階)として、1. ショック期、2. 喪失期、3. 閉じこもり期、4. 再生期がある。
繰り返し
相手の言葉を そのまま繰り返すことで、理解していることを伝える技術。(「料理の盛り付けが気になったんです。」→「盛り付けが気になったんですね。」など)
グループダイナミクス
グループ内での人々の相互作用や関係性、行動のパターンを指す心理学の概念
クロイツフェルト・ヤコブ病
プリオン蛋白が原因とされている認知症の進行が急速的である特徴を持つ疾患
クロックポジション
視覚障害者に食事の位置を時計の文字盤に見立てて「12時の方向にごはん、3時に味噌汁」などと説明する方法
ケアハウス
60歳以上の比較的自立した高齢者が対象で、食事や生活相談、見守り支援などがついた住宅型施設。バリアフリー構造で、プライバシーが確保された個室があり、将来介護が必要になったときは、外部の介護保険サービスを利用できる。
ケアハラスメント
利用者からの介護福祉職に対して行う身体的暴力やセクシャルハラスメントなどのこと
計画相談支援
施設や地域での生活を続けるために、利用者のニーズに応じてサービス等利用計画を作成・見直す支援
経管栄養
経口摂取が十分でない人に対して栄養状態の維持改善を目的とした消化管内にチューブを挿入し栄養剤を注入すること。経鼻経管栄養、胃ろう経管栄養、腸ろう経管栄養の種類がある。
経済的虐待
必要な金銭を渡さない、理由なく金銭の使用を制限する行為
経済的自立
収入を得て、それを適切に管理しながら自己の生活を維持できること
頸髄損傷
脊髄損傷の一種で、頸髄が損傷することで、四肢麻痺や呼吸機能の低下など、さまざまな身体機能の麻痺が生じる状態。主な症状として、運動麻痺や感覚障害、排泄障害、自律神経障害、呼吸障害がある。
傾眠
外部からの刺激がないと目を覚まさず、覚醒してもすぐに眠ってしまう状態のこと。
傾聴
相手の気持ちを理解しようとする姿勢で話を聞くこと。技法として、身体的な姿勢、言葉によるもの、感情への共感、沈黙の活用などがある。
軽度認知障害
記憶などの軽度な認知機能の低下はあるが、認知症ではなく、日常生活は問題なく送ることができている状態
軽費老人ホーム(A型)
身寄りのない高齢者や、家族の支援を受けにくい高齢者が、低料金で生活支援を受けながら暮らせる施設。A型は、食事の提供や生活相談などのサービスが付き、自立または軽度の介護が必要な方が対象。
痙攣性(緊張性)便秘
ストレスなどで腸が過緊張状態になり、便がスムーズに移動できなくなる便秘。
結核
結核菌によって主に肺に感染し、空気感染で広がる慢性の感染症
結晶性知能
経験や学習によって蓄積された知識や語彙、判断力などを活用する能力
結腸の蠕動運動
結腸における筋肉の収縮運動で、便を肛門方向に推進する働き
幻覚
実際には存在していないものが存在しているような状態
言語コミュニケーション
話し言葉や書き言葉、質問や応答などのコミュニケーション技法のこと
健康
WHOによる肉体的、精神的、そして社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病や病弱がないことを意味するものではないといった状態のこと
健康寿命
病気や介護に頼らず、日常生活を自立して送れる期間のこと。
言語聴覚士(ST)
発声・言語・聴覚・嚥下機能の評価や訓練を行い、コミュニケーションや食事の機能を向上させる専門職。主な役割として、言語・聴覚・発声や嚥下などの機能回復を支援し、コミュニケーションや食事の困難に対するリハビリを行う専門職。医療・介護スタッフと連携しながら支援を行う。
原始反射
吸啜反射や把握反射など、生後すぐに見られる刺激に対する反射のこと。生後6ヶ月頃に消失するのが特徴。
倦怠感
いつもの生活が送りづらいと感じるような、全身の疲労感やだるさ
見当識
時間、場所、目の前の人物との関係など自分の置かれた状況が分かることをいう。
見当識障害
時間・場所・人物などの認識ができなくなる状態。自分のいる場所が理解できないなど。
語彙爆発
1歳半~2歳ごろにかけて、新しい言葉が急速に増える時期のこと
構音障害
発声にかかわる器官が何らかの障害によって機能しなくなり、言葉をはっきり発音する能力が失われる障害。発音がはっきりしない、話すペースが不自然、声の出し方に問題がある、と言った症状が見られる。
後期高齢者医療制度
高齢者が健康で自立した生活を送れるようにすることと、必要な医療サービスを受けられる環境を整えることが目的であり、75歳以上の高齢者(および65歳以上で一定の障害がある人)が対象となる公的医療保険制度
抗凝固薬
血液を固まりにくくする薬
公共職業安定所(ハローワーク)
求職者への職業紹介や雇用保険の手続きなどを行い、就労支援を担う国の機関
攻撃
適応機制の1つでもあり、自分の欲求が満たされない時に、自傷行為や他者へ感情をぶつけたりする働き
向社会的行動
助けたり分け合ったりするなど、他者の利益を考えた行動のこと
公衆衛生及び医療
社会保障制度の1つで、感染症予防や医療体制の整備などを通じて、国民の健康を守り、社会全体の健康リスクを減らすことを目的とする制度。保健所の運営や感染症対策などがある。
高次脳機能障害
脳の特定の部分や機能が障害され、思考や言語、記憶などの高度な認知能力に影響を与える状態のこと
抗重力筋
立位姿勢を維持するための筋肉のこと
更生施設
経済的困窮や身体的・精神的な問題を抱えた人が 自立を目指すための支援を受ける施設。生活支援や職業訓練が提供され、社会復帰を促す役割を担う。
公助
地域包括ケアシステムの1つで、社会福祉制度や生活保護など行政による支援をいう。
更生医療
障害のある人が日常生活や社会生活に適応できるようにするための医療支援
抗精神病薬
統合失調症や双極性障害などの精神疾患の治療に用いられ、主に幻覚や妄想、不安、衝動的な行動などを抑えるための薬
構成失行
図形や物体を組み立てたり描いたりすることができない状態
行動援護
障害者総合支援法における「介護給付」サービスの一つで、知的・精神障害があり常時介護が必要な人に対し、行動中の危険回避や外出時の介護、排泄・食事などを支援するサービス。原則、障害支援区分3以上。
行動・心理症状(BPSD)
認知症の中核症状に加えて、環境や周囲の人々との関わりなどの中で、感情的な反応や行動上の反応がみられる二次的症状のこと。心理症状として、抑うつや不安、興奮や妄想などがあり、行動症状として、徘徊や睡眠障害、不潔行為や暴言・暴力などがある。
後頭葉
視覚野や視覚連合野などがあり、視覚情報の認識などの機能がある。
抗認知症薬
アルツハイマー型認知症などにおける中核症状(記憶障害、見当識障害など)を改善・進行を遅らせるための治療薬
抗ヒスタミン薬
アレルギー症状の緩和やアレルギー反応の抑制に使用され、副作用として眠気やだるさを引き起こすともされる薬
幸福追求権
日本国憲法第13条にうたわれている権利
合理的配慮
障害者が他の人と平等に社会参加できるよう、個々のニーズに応じて提供される調整や配慮のこと。目的の1つとして、障がいのある人が他の人と同じ権利や機会を享受できるようにすることがある。
高齢者虐待防止法
高齢者への虐待を防止し、虐待を受けた高齢者の保護や支援を行うことを目的とした法律。虐待の種類として、身体的虐待、心理的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、経済的虐待、性的虐待の種類がある。
誤嚥
飲食物が食道に入らずに喉頭や気管に入ってしまうこと
コーピング
自分の身を守る手段でもあり、ストレスに対して対処するための行動
呼吸
体外から酸素を取り込み、体内で利用し、二酸化炭素を排出する生命維持のプロセス。一般的な呼吸回数は成人で1分間に約12〜18回/分であり、25回以上のことを頻呼吸、12回以下のことを徐呼吸という。
呼吸筋
主動作筋は横隔膜、補助動作筋には、肋間筋、腹筋、胸鎖乳突筋などがある。
互助
地域包括ケアシステムの1つで、地域住民やボランティアなど人と人との支え合いのことをいう。
個人情報
名前や住所、生年月日、家族や緊急の連絡先、健康状態、障害や病歴、介護度や認定情報、ADLやケアプランの内容、マイナンバー、顔写真、クレジットカード番号、運転免許証番号などある。
五大栄養素
三大栄養素にビタミン・ミネラルを加えた5つの栄養素で、健康維持に不可欠な栄養の基本構成
骨格筋
上腕二頭筋、大腿四頭筋など、骨にくっついて体を動かす随意筋
国家扶助(公的扶助)
社会保障制度の1つで、生活に困窮している人に対し、最低限の生活を保障するために国が直接支援を行う制度。生活保護がある。
骨芽細胞
骨の細胞について、日々新しい骨を作る役割がある細胞
骨粗鬆症
骨密度が低下し、骨が脆くなる疾患。閉経後の女性に多く、エストロゲン減少で骨密度が低下しやすくなる。
古典的条件付け
例えばパブロフの犬の実験のように、特定の刺激によって受動的な反応を引き起こす条件付けのこと
個別援助計画
介護サービス計画(ケアプラン)を基に、利用者ごとの具体的な支援内容やサービスの提供方法をまとめた計画のこと。サービスや職種によって名称が異なり、看護計画、リハビリテーション計画、訪問介護計画などがある。
個別性
個々の人の特性や特徴を重視すること
コラーゲン(たんぱく質)
骨の弾力性や柔軟性を保つ
混合性難聴
伝音性難聴と感音性難聴が混在した難聴のこと
コンサルテーション
専門家に相談し、助言を受けることで課題を解決するプロセス
さ〜そ
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
バリアフリー設計の住まいに加えて、見守りや生活相談といった基本的なサービスが提供される高齢者向けの住宅
罪業妄想
自分が罪を犯した、自分に関係ない事故や失敗などを自分の責任と思い込む妄想
サイドケイン(ウォーカーケイン、杖型歩行器)
支持部が広く、体の横で支える片麻痺の人などに使われる杖のこと。T字杖よりも安定感がある。
作業記憶(ワーキングメモリー)
脳内で情報を一時的かつ数秒ほど保持したり処理する記憶
作業療法士(OT)
日常生活に必要な動作の維持・向上を支援するリハビリ専門職。主な役割として、応用的動作(食事・着替え・トイレなど)の改善を目的としたリハビリを行う。
サクセスフルエイジング
老化を受け入れながら健康を保ち、社会に積極的に関わり、充実した人生を送ること。
差し込み便器
座位を保つことが難しい利用者が、ベッド上で排便を行う際に使用される福祉用具
サルコペニア
加齢に伴う筋肉量と筋力の減少を指す。
残存機能
病気や障害によって一部機能が損なわれた状態でも、まだ残っている機能や能力のこと。
三大栄養素
炭水化物・脂質・たんぱく質の3つを指し、体を動かすエネルギー源や体の構成成分となる基本的な栄養素
次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)
強力な殺菌・消毒作用をもつ薬剤。手すり・ドアノブなどの環境表面の消毒や嘔吐物や血液などの感染対策、衣類や器具の漂白・除菌などの用途がある。
CDR(Clinical Dementia Rating)
認知症の重症度を評価するためのスケール(評価法)で、認知機能や日常生活の状況をもとに、0〜3の5段階で総合的に判定する。0は正常、0.5は軽度認知障害、1〜3は認知症。
ジェノグラム
家族構成を理解し、家族内の関係や状況などを把握するために家族構成や家族内の関係性を図式化したもの
ジェロントフォビア
高齢者や高齢になることに対する過度な恐怖や嫌悪感を指す心理的な状態をいう。
弛緩性便秘
便秘の種類のうち、腸の機能低下が原因で生じる便秘
事業継続計画(BCP)
継続的にサービスが提供できるための災害対策
視空間認知障害
視覚情報の処理や空間の位置関係の理解が困難になる状態。歩道や障害物との距離感を誤り転倒しやすくなったり、絵や地図の配置や方向が理解しにくくなる。
自己中心性
自分の考えや視点が、相手にとっても同じであると錯覚してしまう傾向のこと
自己開示
コミュニケーションを通して自分の考えや感情などの情報を、自分から他者に伝えること。相手と自分の心理的距離を近づけ、信頼関係を作るための手段。
自己覚知
自分の価値観や考え方などを知ること
視床下部
自律神経やホルモン分泌の調整(体温・睡眠・摂食・性行動)や扁桃体と連携して情動反応の身体的変化(心拍・発汗など)に関与。
脂質
ホルモンや細胞膜の材料となり、1gあたり9kcalのエネルギーを持つ栄養素
四肢麻痺
頸髄損傷など、両手両足すべてに麻痺が生じ、全身の運動が制限される状態。
自助
地域包括ケアシステムの1つで、何かをする、健康管理、市場サービスの購入など、自分自身で行うことをいう。
耳小骨
中耳にある3つの小さな骨のこと。ツチ骨(槌骨)、キヌタ骨(砧骨)、アブミ骨(鐙骨)の3つ。鼓膜が受け取った音の振動を内耳に伝える役割を持つ。
姿勢反射障害
バランスが悪くなり、転びやすくなること。パーキンソン病4大症状の1つでもある。
施設サービス
介護が必要な人が施設に入所し、生活全般の支援や医療的ケアを受けるサービス。介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院がある。
死前喘鳴
終末期や死の直前に、ゼーゼー・ゴロゴロとした呼吸音が聞こえる現象。
失語
主に左脳の障害によって、言葉を理解したり、話したり、読む・書くことがうまくできなくなる障害のこと
失行
認知症の中核症状でもある運動機能には問題がないが、脳の問題によって、目的に合った動作や運動ができない状態
失語症
脳の言語中枢の障害で起こる言語障害
実質的違法性阻却
社会福祉士及び介護福祉士法において、医師の指示の下、一定の条件を満たした場合に喀痰吸引や経管栄養などの医療行為を介護福祉士等に行わせることが認められる考え方
実行機能障害
目的をもって物事を計画・判断・実行する力(=実行機能)が低下する状態のこと。
嫉妬妄想
夫や妻が浮気しているに違いない等と思い込む妄想
失認
感覚器官(目・耳など)が正常なのに、見たり聞いたりしても、それが何かが認識できない障害のこと。
児童福祉法
すべての児童が健やかに成長できるよう、保護・育成・支援を目的とし、児童福祉施設の整備や福祉サービスの提供を定めた法律
死の受容の5段階モデル
キューブラーロスが提唱したもので、死に直面した人が示す心理的反応を「否認・怒り・取引・抑うつ・受容」の5つの段階で説明した理論
自閉症スペクトラム障害(ASD)
コミュニケーションや対人関係が難しい、強いこだわり、パターン化した行動などの特徴を持つ障害
社会福祉士
相談支援を通じて福祉サービスの調整や生活支援を行う専門職。主な役割として、利用者や家族の相談支援を行い、入所・退所時の調整、関係機関との連携を担当。
社会福祉士及び介護福祉士の義務等
1誠実義務、2信用失墜行為の禁止、3秘密保持義務、4連携、5資質向上の責務、6名称の使用制限、7保健師助産師看護師法との関係、8喀痰吸引等業務の登録がある。
若年性認知症
65歳未満で発症する認知症
周期性四肢運動障害
睡眠中に下肢が勝手にピクピクと動いてしまう特徴の睡眠障害
準言語コミュニケーション
声のトーンや話すスピード、音量などのコミュニケーション技法のこと
準備的共感
利用者の生活歴等を把握し、相手の立場に立ちどのような心理的状況かを考え共感する準備をすること
受容
相手の考えや感情など否定せず、言動や感情をそのまま受け止めること
終末期
病気からの回復が見込めず、死を迎える間際の時期
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
高齢者の活動範囲や介助の必要度をもとに、日中の生活状況をランクで示す指標。自立度が高い順から、ランク J(自立)、ランク A(準寝たきり)、ランク B(寝たきり)、ランク C(全介助)とある。
障害児
身体・知的・精神(発達障害を含む)に障害のある18歳未満の児童、
または治療方法が確立していない疾病などにより特別な支援が必要な児童のこと。(児童福祉法)
障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)などにより、日常生活や社会生活に制限のある者であって、継続的な支援を必要とする人。(障害者基本法)
障害者基本法
すべての障害者の権利を保障し、差別の解消や社会参加の促進を目的として、障害者福祉の基本理念を定めた法律。
障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消を推進し、「全ての人々が平等に社会参加できる共生社会の実現」を目指すために制定された法律
障害者総合支援法
障害のある人々が健やかな生活を送り、社会参加を促進するための施策を総合的に推進するための法律
小規模多機能型居宅介護
泊まりを中心とし、通い、訪問といったサービスを適切に組み合わせて提供する介護サービス
小腸の構造
十二指腸、空腸、回腸の順
情動焦点型コーピング
ストレスによって生じる感情を和らげるために、気分転換や趣味などで心を整える方法
触手話
盲ろう者に適したコミュニケーション方法
褥瘡
長時間同じ姿勢でいることにより、皮膚やその下の組織が圧迫され、血流が悪くなって壊死してしまう状態のこと。好発部位は仙骨部。主な原因は、圧迫・ずれ・摩擦・湿気がある。
所属・愛情の欲求
マズローの5段階欲求説のうちの、家族や恋人、同僚などの一員に加わりたいといった欲求
ジョハリの窓
自己と他者の間での情報の共有を通じて、自己理解や対人関係を改善するためのモデル。特に自己開示とフィードバックが重要であり、開放の窓を広げることが円滑なコミュニケーションにつながる。開放の窓、盲点の窓、秘密の窓、未知の窓の4つがある。
社会資源
人材や資金、施設、制度など、日常生活上の人々が抱えている様々な問題を解決する福祉サービスの総称。フォーマルサービス(公的サービス)とインフォーマルサービス(私的サービス)がある。
社会的参照
子どもが不安や迷いを感じたときに、他者(特に親や養育者)の表情や行動から状況を判断し、行動を決定すること
社会的自立
社会の一員として責任ある行動をとり、人との関わりの中で適切に意思決定できること
社会福祉
社会保障制度の1つで、高齢者、障害者、児童など特別な支援を必要とする人々に対し、福祉サービスを提供し、生活の質を向上させる制度。
社会福祉基礎構造改革
措置制度から契約制度への転換や介護保険制度の導入、福祉サービス市場の開放など、利用者の選択権とサービス提供の多様化を実現し、より柔軟で質の高い福祉サービスの提供を目指した大規模な改革
社会保険
社会保障制度の1つで、病気・失業・老齢・障害などのリスクに備え、保険料を納めることで必要な給付を受けられる制度。年金保険や医療保険、雇用保険などがある。
弱視
メガネやコンタクトをしても視力が改善されない状態
重度訪問介護
障害者総合支援法のサービスであり、重度の身体障害者や知的障害者を対象に、日常生活や外出時の支援などを包括的に提供するサービス。障害支援区分は4以上。
集団凝集性
グループのメンバーが互いに結びつき、グループとしての一体感や団結力を持つこと
就労継続支援A型
雇用契約を結び、賃金を得ながら働く障害者を対象とした支援サービス
就労定着支援
長期間働き続けられることが目的であり、障害や社会的困難などの理由で職場での定着が難しい人々を支援するための取り組み
昇華
適応機制の1つでもあり、社会的に認められない欲求などを社会的に価値がある内容に置き換えて欲求を満たそうとする働きのこと。
生涯現役社会
年齢に関係なく、働く意欲と能力のある人が、自分の能力を最大限に発揮できる社会のこと
償還払い
利用者が先に全額を事業者に支払い、後から市町村からその額の9割もしくは全額が払い戻される支払い方式
上肢
上腕部、肘、前腕部、手をまとめて呼称
小脳
運動の調整・バランス・姿勢制御などに関与
叙述体
時系列に事実のまま記録する文体のこと
消毒
病原性の微生物を死滅させることもしくは弱めること。アルコール消毒、次亜塩素酸ナトリウム、煮沸消毒などがある。
消費者生活センター
消費者が安全で安心な生活を送れるよう支援し、自らの権利を理解してトラブルに対処できるようサポートする公的機関
初語
1歳前後にこどもが初めて意味のある言葉を発する言葉のこと
ショートステイ
在宅介護の家族の負担軽減が目的でもある、利用者を一時的に施設に預かり、家族が休息できる介護サービス
自立
自己の能力だけでなく、他者の支援や関わりを通して、その人が主体的に生活をしていくこと。身体的、経済的、社会的、生活、精神、性的自立がある。
自立生活運動 (IL運動)
1960年代、アメリカで起こった障害者による「重度の障害があっても自分の人生を自立して生きること」を主張した運動
自立支援
利用者自身が、自分の意思で自己選択や自己決定できるために支援すること
自律神経
意識的な制御なしに体のさまざまな機能を調節する神経系の一部のこと。ストレスや運動時に活発に働く交感神経とリラックス時や睡眠時に働く服交感神経がある。
事例検討
ケースカンファレンスと同義でもあり、様々な専門職種が一堂に会して援助や支援の方向性を検討する機会のこと
自立訓練事業
障害福祉サービスのうち、一定の支援が必要な精神障害や知的障害がある人に対して、地域生活への移行を目的としたサービス
心因性精神障害
心理的なストレスや環境の変化が主な原因で起こる精神的な反応。不安障害や心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害などがある。
心因性尿失禁
精神的なショックやストレスなどが原因として生じる尿失禁
心気妄想
実際には病気ではないが病気であると思い込む妄想
心筋
心臓だけにある不随意筋
心筋梗塞
胸部の圧迫感や痛みや息切れなどの症状があり、心臓の筋肉である心筋が突然の血流の停止によって損傷を受ける状態
心臓機能障害
心臓のポンプ機能に何らかの問題が生じ、十分に血液を全身に送り出せなくなる状態。呼吸困難や息切れ、むくみ(浮腫)などの症状がある。
心臓死
「心臓の停止」「自発呼吸の停止」「瞳孔散大」の3つの要素が一定時間持続した状態
人権
人間としての権利のこと
身体障害者標識(身体障害者マーク)
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマーク
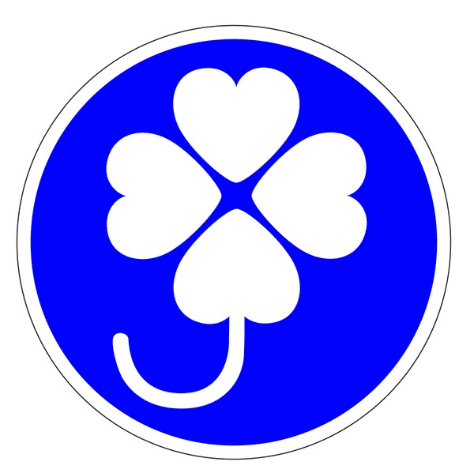
身体障害者
身体上の障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者。(視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害)の5つの分類がある。
身体障害者福祉法
1949年に制定された、身体に障害を持つ人々の生活支援や社会参加を促進するための基本的な法律。
身体的自立
移動や食事、排泄などの基本的な身体動作を自分で行えること
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
生死に関わるような体験をした後に発症する精神的な疾患
心不全
心臓のポンプ機能の低下、つまり心臓の栄養や血液を全身に送る機能が低下している状態。主な症状として、呼吸困難(息切れ)・疲労感や倦怠感・浮腫(むくみ)・チアノーゼ・頻脈などがある。
また、右心不全では下肢の浮腫や頸静脈怒張、腹水、左心不全では呼吸困難(特に起坐呼吸)やチアノーゼ、頻脈などと心臓の部位によって生じる症状が異なる。
遂行機能障害
計画を立てたり、順序立てて物事を進めることが難しくなる状態。買い物リストを作っても活用できないなど
垂直避難誘導
建物内で発生した火災や地震などの災害から利用者を安全に避難させるために、主に階段を使用して上層階や下層階に誘導すること
スクエアオフ
爪をまっすぐに切り、角を少し丸めるようにやすりで削る爪の切り方。巻き爪や深爪を防ぎ、爪の欠けや変形の予防につながる。特に足の爪に適した切り方である。
スーパーバイザー
介護現場において、例えば新人職員など、スタッフを指導したり監督する役割を持つ人のこと
スーパービジョン
上位の立場にある指導者(スーパーバイザー)が、部下や後輩(スーパーバイジー)に対して助言・指導・支援を行い、成長を促すプロセスのこと
ストレングス
能力や意欲、その人が有する社会資源など、その人が持っている力のこと
ストーマ
手術で腸や尿管を体外に導き作られた便や尿の排泄口のこと。消化管ストーマ(人工肛門)や尿路ストーマ(人工膀胱)がある。
SPELLの原則(Structure、Positive、Empathy、Low Arousal、Links)
ASD(自閉症スペクトラム症)をはじめとする発達障害のある人への支援において重要とされる5つの要素、構造化、肯定的、共感的、穏やか、つながりの頭文字を取った原則
スライディングボード
ベッドと車椅子の間などで利用者を移乗させる際、臀部の摩擦を減らし、介助者の負担を軽減しつつ、安定した移乗を助ける福祉用具
生活課題(ニーズ)
利用者が望む生活のために生活上の解決すべき課題のこと
生活協同組合
食品や日用品の供給、福祉サービスなどを通じて、組合員の生活向上を目指す共同事業体
生活習慣病
不健康な食事や運動不足、睡眠不足など、普段の生活習慣等が原因となる疾患の総称
生活的自立
身の回りのことを自分で行い、日常生活を自立して営むこと
生活の質(QOL)
人々が幸福や満足感を感じる程度や、生活の充実度を示す指標
生活保護
生活に困窮する人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立を支援する制度
清拭
全身または部分的に身体を拭いて清潔を保つケア方法。
正常圧水頭症
歩行障害、認知症、尿失禁の3つの症状が主な特徴で、脳脊髄液の循環障害によって発症し、シャント術による治療が効果的な疾患
精神障害
精神疾患によって精神機能の障害が起こり日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のこと
精神障害者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者
精神的健康
メンタルヘルスやこころの健康状態
精神的自立
日常の問題に対して自ら判断し、意思決定を行えること
精神保健福祉士
精神疾患や精神的困難を抱える人の相談・支援を行い、福祉サービスの利用を調整する専門職。主な役割として、利用者の精神的な課題を把握し、適切な社会資源の活用を支援する。
精神保健福祉センター
精神疾患や心の健康に関する相談・支援・啓発を行う専門的な公的機関
精神保健福祉法
精神疾患を持つ人の治療・社会復帰を促進し、地域での生活を支援するために、医療・福祉サービスの提供を定めた法律。
静水圧作用
水の重さによる身体に発生する水圧のこと。血液の循環が良くなり、心臓や肺の働きが活発になる効果がある。
生存権
憲法25条に基づき、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことを国に求めることができる権利
性同一性障害
性別不一致ともいい、個人の性別に対する自己認識(性同一性)と生物学的な性(出生時の性別)との間に不一致がある状態
成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人々の財産管理や契約手続き、福祉サービスの利用を支援するために、家庭裁判所が選任した後見人が適切な意思決定をサポートする制度。法定後見制度と任意後見制度の2つがある
生命維持機能
家族の機能について、食欲や性欲の充足などに関する機能のこと
性的自立
自分の性を理解し、他者の性も尊重した上で責任ある行動をとること
世界保健機関(WHO)
1948年に設立され、公衆衛生や感染症対策、健康促進を目的とし、すべての人々が最高の健康水準に達することを目指す国際機関
積極的安楽死
本人の意思にもとづいて、苦痛から逃れるために致死性のある薬物を使い死に至ること
摂食嚥下の5期モデル
摂食嚥下は、先行期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期の5つのステージがある
背抜き(圧抜き)
圧分散や身体の筋緊張の緩和の効果がある、ベッド上で利用者の体を持ち上げたり移動させる技術
セルツメント
19世紀後半に始まった活動で、貧困地域に住み込んで実態調査を行いながら、住民への教育や生活支援を提供するという取り組み
セルフヘルプグループ
同じ病気や障害、悩みを抱える当事者同士が自主的に集まり、経験や悩みを分かち合い、問題解決を図る集団のこと。断酒会や精神疾患、薬物依存症、LGBT、若年性認知症、がん患者、非虐待者など多岐にわたる。
全身性エリテマトーデス(SLE)
全身性炎症性疾患で、女性の発症が多く、蝶形紅斑、関節痛や関節炎、強い疲労感が特徴的な疾患
センタリング
介護者が自身の感情や状態をコントロールするための技法
全人間的復権
社会的に排除されてきた人々の権利や尊厳を回復するための運動や考え方。リハビリテーションの理念として、位置付けられている。
選択的注意
必要な情報に注意を向け、不必要な情報を無視する能力
前頭葉
運動野や運動性言語野(ブローカ野)などがあり、運動や思考、注意、判断などの機能がある。
喘鳴
ゼーゼー、ヒューヒューといった音であり、喘息、COPDなど気道が狭くなったときに聞こえる高い音のこと。
せん毛運動
吸い込んだ細菌やウイルスを気管粘膜で排除する動きのこと
相談支援事業
障害のある人やその家族の相談に応じ、適切な福祉サービスの利用計画を作成する支援
相談支援専門員
障害者支援においてサービス等利用計画を作成し、その計画に基づいてサービスを提供するために関係者との調整を行う専門職
前頭側頭型認知症
前頭葉や側頭葉の神経細胞が萎縮することで、人格や行動の変化、感情のコントロールの障害、言語障害 などが現れる認知症。行動異常や社会性の低下が特徴的な症状である。
せん妄
病気や薬、何らかの理由によって突然意識障害や認知機能の低下が生じること
総義歯
すべての歯を失った人が使用する取り外し可能な人工の歯(義歯)のこと。部分的に歯を失った場合に使用する義歯を部分義歯。
相貌失認
顔を見てもそれが誰の顔かを認識できない状態(失認の一種)
側頭葉
聴覚野や感覚性言語野(ウェルニッケ野)があり、聴覚や言葉の理解、記憶などの機能を持つ。
ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)
ノーマライゼーションの発展系とも言われ、フランスで生まれた、あらゆる人々が社会の一員として認められ、尊重され、機会均等に参加できるようにすることを目指す考え方
ソーシャルロール・バロリゼーション
障害者や不利な立場にある人たちに社会で大切な役割を与え、その人たちの尊敬や地位を高めることを目的とした考え方。ドイツ出身のヴォルフェンスベルガーが提唱。
SOAP方式
主観的情報、客観的情報、評価、計画のそれぞれの頭文字をとった利用者の経過記録の書き方
SOLERの技法
傾聴において相手へ関心や尊重を示すための非言語コミュニケーションを具体化した技法。Squarely(真っ直ぐ)、Open(開放的)、Lean(姿勢を傾ける)、Eye Contact(視線)、Relaxed(リラックス)がある。
組織図
組織を運営するにあたり、全体の指揮命令系統を把握するために必要な図
措置入院
自傷他害のおそれがあると認められた場合に、都道府県知事の権限で行われる入院。2名以上の精神保健指定医の診察が必要。
ソロモン
1970年代にソーシャルワーク分野でのエンパワメントの重要性を指摘する
尊厳
個々の人間が持つ価値や尊重されるべき存在であるという考え方
尊厳死
自らの意思で延命処置を行うだけの治療は受けずに、自然な経過で死を迎えること
た〜と
ダーウィン
イギリスの自然科学者であり、「種の起源」の著者、そして進化論を提唱した人物
ターミナルケア
病気で余命がわずかな人に対して、延命治療はせず、その人が自分らしい形で最期を迎えられるように支援すること
退行
適応機制の1つでもあり、自分の行動したいという欲求が継続的に制限されることで、できることでも自分でしようとせず、他者に依存し甘えるような言動をとるようになること。
体循環
左心室から始まり、全身の毛細血管、そして右心房といった血液の循環のこと
帯状疱疹
主に水痘ウイルスが原因であり、体の片側に神経に沿って帯状に痛みや発疹(水ぶくれ)が現れる疾患
体位ドレナージ
仰臥位から側臥位への体位変換など、重力を利用して効率よく痰の排出を促す方法
大脳基底核
大脳の深部にある神経核の集まりで、運動の調節、姿勢の維持、学習や認知機能にも関与する脳の構造のこと
大脳辺縁系
感情・記憶・動機づけに関与する脳の構造の総称で、扁桃体や海馬、視床下部などが含まれる
対面法
真正面に座って面談する方法。介護職と利用者が向かい合う形で座るため、形式的な面接や相談に適している。
ダウン症(21トリソミー)
21番目の染色体が通常2本のところ3本になることが原因とされる先天性疾患
他職種連携
複数の領域の専門職者が各々の技術と役割をもとに、共通の目標を目指す協働のこと
脱水
体内に必要とされる水分や電解質が不足している状態
脱抑制
状況に対する反応としての衝動や感情を抑えることが不能になった状態のこと
タッチング
コミュニケーションの中に手を触ったり、体の一部に触れることで相手の安心感を増やすための方法。
多様性
様々な違いや特性を持つ人々が存在し、その違いを尊重し受け入れること
短期記憶
短期間で情報を得る記憶
短期目標
長期目標達成までの踏むべき各段階の目標のこと
炭水化物(糖質)
脳や神経の主要なエネルギー源。糖質と食物繊維に分けられ、糖質はエネルギーになり、食物繊維は整腸作用がある。
たんぱく質
身体のさまざまな組織の主成分で、筋肉や爪、臓器、血液、ホルモンや遺伝子などの原料ともなる栄養素
単麻痺
神経や脳の局所的な障害など、片方の手または足のみに麻痺が生じる状態。
チアノーゼ
血液中の酸素不足により、皮膚や粘膜が青紫色になる症状のこと
地域移行支援
障害者が入所施設や病院から地域での生活へ移行するために、住居の確保や生活環境の調整などを支援するサービス
地域活動支援センター
障害のある人が創作・生産活動や地域交流を行いながら、社会参加を促進する場として位置づけられるサービス
地域共生社会
すべての人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら共に暮らし、包摂的なコミュニティを形成する社会のこと
地域生活定着支援センター
刑務所などから出所した人や、社会的孤立状態にある人に 住居・生活支援を提供する施設。福祉サービスの利用につなげるなど、地域での自立を支援する。
地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を支援するため、地域限定で提供されるサービス。小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがある。
地域定着支援
単身での地域生活を始めた障害者に対して、緊急時の対応や見守りを行い、安心して暮らし続けられるよう支援するサービス
地域包括ケアシステム
高齢者が地域で自立した生活を送るために、医療、介護、介護予防、住まい、日常生活の5つの支援が包括的に提供される体制のこと。また、自助、互助、共助、公助の4つの助がある。
地域包括支援センター
市町村が主体となり、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーらが、住民の健康維持と生活の安定を支援し、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に行う施設。主な役割として、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防・ケアマネジメント業務、多面的(制度横断的)支援の展開、介護予防支援など多岐にわたる。
窒息
外部の物質による気道の閉塞や肺の機能障害など、呼吸の停止や制限によって体内に酸素が供給されない状態
チェーン・ストークス呼吸
速く深い呼吸(過呼吸)と無呼吸が交互に繰り返される異常な呼吸パターン
着患脱健
麻痺や障害のある側(患側)から衣服を着て(着患)、健常な側(健側)から脱ぐ(脱健)という、衣服の着脱時の基本的な介助の原則
知的障害
IQ70未満が特徴であり、18歳未満の発達期に生じる知的機能の低下や、それに伴う社会適応の困難が特徴とされる障害
知的障害児(者)
厚労省の基礎調査より、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障があり、特別な援助を必要とする状態をさす。
知的障害者福祉法
知的障害がある人が社会参加し、生活の質を向上できるように、福祉サービスや支援の仕組みを定めた法律。1960年に精神薄弱者福祉法として制定され、1998年に今の名称となる。
知能
問題を解決したり、環境に適応したり、学習・理解する能力全般のこと
着衣失行
「服を着る」動作が分からなくなる失行
注意欠陥多動性障害(ADHD)
注意力の持続が困難で多動性や衝動性が見られる発達障害。12歳までに発症が見られ、特に男児に多い
注意障害
他の刺激に気が移りやすく、注意力が散漫になる障害のこと
中途覚醒
眠りについてからすぐに目が覚めてしまう睡眠障害
昼夜逆転
日中に活動し夜間に睡眠を取る、生活リズムが反転してしまう状態
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマーク
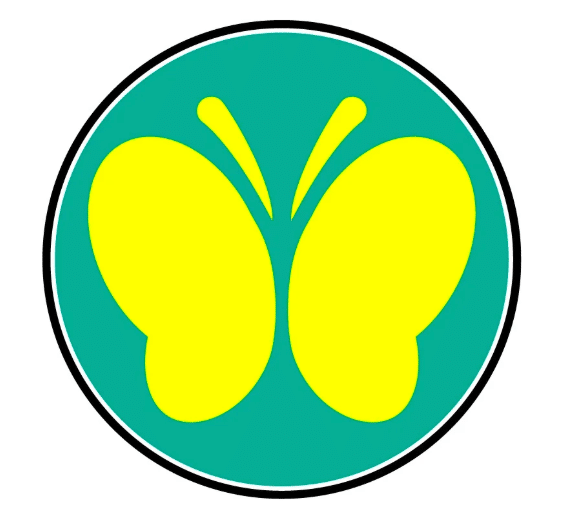
長期臥床
病気や障害により6か月以上ベッド上での生活が続く状態(≒寝たきり)
超高齢化社会
高齢化率が21%を超えた社会のこと
直角法
テーブルの角などをはさんで斜めに座って行う面談形式。視線を外しやすく、利用者との関係づくりに適している特徴を持つ。
直腸性便秘
便意を我慢する習慣や排便反射の低下により、便が直腸に溜まっても排出できなくなる状態。
直腸の排便反射
直腸に便が溜まると引き起こされる反射で、便を体外に排出するための反応
直面化
利用者の感情と行動の矛盾点を指摘するコミュニケーション法
貯痰音
ゴロゴロした音であり、気道に痰(分泌物)が溜まっているときに聞こえる音のこと。
陳述記憶
記憶の内容を言葉で説明ができる記憶
対麻痺
脊髄損傷など、両足に麻痺が生じ、歩行や立位が困難になる状態。
T字杖
グリップがT字型になっている最も一般的な一本杖のこと。軽いバランス補助などに使われる。
適応機制(防衛機制)
逃避や合理化、反動形成や感情転移など、無意識下において不安やストレスなどから自分の心を守り安定させる働きのこと
デスカンファレンス
利用者の死亡後に開催され、利用者の経過や関わりなどを振り返る機会のこと
手続き記憶
非陳述記憶の一部であり、過去に体験したことがあり、身体で覚えた動作の記憶
転移
利用者が介護者に感情を向けること
展望記憶
未来に予定されている内容の記憶
投影
適応機制のうちの1つである、自分の思いや欲求、感情を他者に映し出し、その人がそれを持っていると感じること
同行援護
障害福祉サービスの「介護給付」に分類され、視覚障害者が外出する際に、資格を持つガイドヘルパーが付き添い、安全な移動や日常生活上の支援を行う障害福祉サービス
動作緩慢
動作全体がゆっくりとなること
頭頂葉
体性感覚野や味覚野や頭頂連合野などがあり、さまざまな感覚を統合して認知、物事を見極めたりや空間認知などの機能を持つ。
導尿
カテーテルを尿道にいれて膀胱内の尿を体外に排出すること
同名半盲
脳の損傷により、両目の同じ側の視野(右半分または左半分)が見えなくなる視野障害のこと
透明文字盤
透明な板に50音、用事ごとや言葉などが書かれており、それを指さしたり文字盤を介して視線を合わせることでコミュニケーションをはかる道具のこと
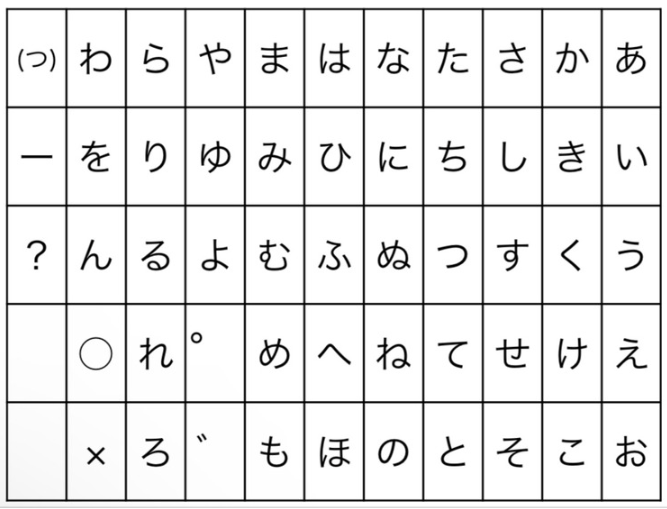
ドーパミン
「快楽」「意欲」「運動調節」などに関与する脳内で働く神経伝達物質
閉じられた質問
「はい」か「いいえ」、2〜3単語くらいで答えられるような質問のこと。主な特徴として、短時間で済む、回答が簡単にできるなどがある。例えば、「この本は好きですか?」。
特定疾病
1がん(がん末期)、2関節リウマチ、3筋萎縮性側索硬化症(ALS)、4後縦靱帯骨化症、5骨折を伴う骨粗鬆症、6初老期における認知症、7進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病、8脊髄小脳変性症、9脊柱管狭窄症、10早老症、11多系統萎縮症(MSA)、12糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、13脳血管疾患、14閉塞性動脈硬化症、15慢性閉塞性肺疾患、16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症の16種類ある。
特別徴収
第1号被保険者のうち、年金額が年額18万円未満の場合の徴収方法
ドライマウス
さまざまな原因によって、唾液分泌量が減少し、口腔内が乾燥しやすくなる状態
トルク
物体を回転させるときに必要な「回す力」のこと。力とその力を加える点から回転軸までの距離によって変わる。
トルクの原理
力を加える位置が回転軸から遠いほど、少ない力で大きな回転力(トルク)を生み出せるという仕組み
な〜の
内因性精神障害
脳や神経の器質的な病変は見られず、はっきりした外的原因がないのに発症する精神疾患。統合失調症や双極性障害(躁うつ病)、うつ病などがある。
内呼吸
血液と細胞とのガス交換
ナショナルミニマム
憲法25条に基づき、国が全国民に保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の水準
ナトリウム
体液の浸透圧の調節、血圧の維持、筋肉の収縮などのはたらきをもつ無機質
七草粥
1月7日の人日の節句に無病息災を祈って食べる料理
喃語
生後6か月頃からみられる、「アーアー」「バブバブ」など意味をなさない音のこと
二語文
2歳ごろからみられ、「ママ、だっこ」などの2つの単語からなる文のこと
日常生活自立支援事業
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な人に対して、地域で自立した生活が送れるように支援していく事業。具体的には、生活支援員による金銭管理や公共料金の支払い、預金の出し入れ、契約の手続きなどがある。
日本介護福祉士会倫理綱領
専門職としての知識・技術と倫理意識を基に、最善の介護福祉サービスを提供し、人々の豊かな暮らしを支えることを目指した指針。①利用者本位・自立支援、②専門的サービスの提供、③プライバシーの保護、④総合的サービスの提供と積極的な連携・協力、⑤利用者ニーズの代弁、⑥地域福祉の推進、⑦後継者の育成がある。
尿失禁
尿が意図せずに漏れる状態
尿路感染症
尿路(尿道、膀胱、尿管、腎臓)のどこかに細菌が感染することによって引き起こされる感染症。主な症状として、排尿時痛や頻尿や残尿感、血尿や混濁尿などがある。膀胱炎や尿道炎などは下部尿路感染症、高熱や腰痛・背部痛は腎盂腎炎など上部尿路感染症でよく見られる症状。
任意後見制度
判断能力が十分あるうちに、将来の支援内容を信頼できる人(任意後見人)と契約で決める制度
任意入院
患者が自らの意思で同意して行う入院。家族の同意はいらない。
認知機能
脳が情報を処理し、適切な判断や行動を行うための能力のこと。記憶する、考える、判断する、注意を向ける、言葉を理解・使用する、問題を解決するなど
認知機能障害
脳の機能が低下することによって、記憶、思考、理解、判断、言語能力などの認知機能に障害が見られる状態
認知症
様々な原因によって、記憶力や判断力、言語能力、見当識などの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が生じる状態
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
認知症による症状や行動が、日常生活にどの程度影響を与えているかを示す指標。自立度が高い順に、ランク I、ランク II、ランク III、ランク IV、ランク Mとある。
認知症施策推進大綱
認知症の人が尊厳を持って自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指し、国が「共生」と「予防」を両輪として総合的・計画的に認知症施策を推進するために策定した基本方針。5本の柱として、1普及啓発・本人発信支援、2予防、3医療・ケア・介護サービス・介護者への支援、4認知症バリアフリーの推進・若年性認知症への支援・社会参加支援、5研究開発・産業促進・国際展開、がある。
認知症初期集中支援チーム
認知症の初期段階にある方や認知症が疑われる方、その家族を支援するための専門的なチーム。対象者の発見、訪問支援、情報提供とアドバイス、医療受診のサポートといった支援を包括的、集中的(おおむね6ヶ月)に行い、自立生活のサポートをしていく。
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
認知症の高齢者が、少人数(1ユニット9人以下)で共同生活を送りながら、専門スタッフの支援を受けて生活する施設。家庭的な雰囲気の中で、生活リハビリや見守り支援を重視している。
ネグレクト(介護等放棄)
高齢者虐待の分類のうち、本人が必要とする介護やサービスを放棄し身体や精神状態を悪化させる行為
年金事務所
国民年金や厚生年金など、年金の加入・保険料・給付などに関する手続きや相談を受け付ける公的機関
脳卒中
脳の動脈硬化が進み、脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称。症状として、運動麻痺や感覚障害、言語障害、頭痛や顔面の麻痺などがある。例えば、右脳の血管が詰まる(右脳梗塞)ことで、身体の左側に麻痺が生じる(左片麻痺)がみられる。
ノーマライゼーション
障害のある人を含むすべての人が尊重され、地域社会の中で他の市民と同じように普通の生活を送れる社会を目指す理念。デンマーク出身のバンク・ミケルセンが提唱。
ノーマライゼーションの8原理
ニィリエが提唱。①一日のノーマルなリズム、②一週間のノーマルなリズム、③一年間のノーマルなリズム、④ライフサイクルにおけるノーマルな発達経験、⑤ノーマルな個人の尊厳と自己決定権、⑥ノーマルな性的関係、⑦ノーマルな経済水準とそれを得る権利、⑧ノーマルな環境形態と水準がある。
ノロウイルス
感染力が非常に強いウイルス性胃腸炎の原因ウイルス。主な症状として、①急な吐き気・嘔吐、②下痢(水様性)、③腹痛、④発熱(軽度)、⑤倦怠感・脱水症状など
ノンレム睡眠
「深い眠り」で、脳の活動は低下している休息状態。身体の修復・回復、成長ホルモンの分泌、脳の老廃物除去などの役割を持つ
は〜ほ
パーキンソン症状
主に、脳内のドーパミン不足によって発生し、パーキンソン病やその他の神経疾患で見られる特徴的な運動症状の総称
パーキンソン病
脳の指令を伝えるドパミンが減ることで体の動きに障害が生じる病気。4大症状として、安静時振戦、筋固縮、無動・寡動、姿勢反射障害がある。他にも、嚥下障害や便秘や起立性低血圧、うつ状態や認知症といった症状もみられる
パーソン・センタード・ケア
認知症をもつ人を一人の「人」として尊重し、その人の立場に立って考え、その人らしさを大切にしたケアの考え方
肺
呼吸器系の1つで、右肺は上葉・中葉・下葉に分かれており、左肺は2葉に分かれている。
肺活量
1回に吸い込める空気の量
肺循環
右心室から始まり、肺動脈→肺→肺静脈→左心房の順の血液循環のこと
バイステックの7原則
利用者との援助関係を形成する時に必要な原則・考え方。個別化、意図的な感情表出、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度、自己決定、秘密保持がある。
バイタルサイン
脈拍、体温、血圧、意識レベル、呼吸の5つを指標とする生命兆候のこと
廃用症候群
身体が動かない状態が長期間続くことで、体の機能が低下し、それに伴い心身の機能も低下する状態。主な症状として、筋力低下(筋萎縮)や関節拘縮、精神機能の低下(うつ傾向・見当識障害など)、意欲の低下などがある。
ハインリッヒの法則
1件の重大事故の背後には、29件の軽微な事故と300件のヒヤリ・ハット(事故寸前の事例)がある」 という経験則
白内障
加齢に伴い水晶体が白く濁りやすい特徴を持つ眼の疾患
パターナリズム(父権主義)
強い立場の人が弱い者の立場に対して一方的にその行動に介入したり干渉したりすること
ばち状指
肺疾患や心疾患、消化器疾患等でみられ、手や足の指先が肥大し、爪の成長部分の角度が変化した状態
発汗
発汗とは体温を下げるための機能
パニック障害
突然理由もなく激しい不安に襲われて、心臓がドキドキする、めまいがしてふらふらする、呼吸が苦しくなるといった状態
ハヴィガースト
乳幼児期や壮年期、老年期など、人生を6段階に分類し、それぞれの段階ごとに発達課題をまとめた人物
バリア
生活の中で不便に感じること、さまざまな活動をしようとする時の障壁となるもの。物理的、制度的、文化・情報面、意識上などのバリアがある。
バリアフリー
からだの不自由な人や高齢者などが社会生活を送る際に、障害になるものを取り除く社会を目指していく考え
バリアフリー社会
障害者や高齢者などが社会生活をしやすいように、物理的・制度的な障害(バリア)を取り除き、新たなバリアを作らないようにする社会のこと
バリデーション(validation)
認知症の人の感情や行動を否定せずに受け入れ、共感しながらその人の感じている世界に寄り添うケアのこと 。
反映(リフレクション)
コミュニケーション技法の1つで、相手が表現した感情や気持ちを、そのまま言葉にして返すこと。
バンクミケルセン
ノーマライゼーションの父とも呼ばれ、ノーマライゼーションを提唱する
半側空間無視
視力に異常はないにもかかわらず、空間の一側に注意が向かず認識できなくなる状態。例えば、片側に食べ残しがみられたり、移動中にぶつかったりしやすくなる。
ピアサポート
1対1のサポートが多く、同じ経験や課題を持つ個人が、対等な立場でお互いに支援や励ましを提供すること
ピアジェ
認知発達理論を提唱した人物
B型肝炎
肝炎のうち、血液や体液が感染源であり、ワクチンによる予防が可能な特徴を持つ肝炎
PM理論
目標達成機能と集団維持機能を軸にした、三隅二不二が提唱した、リーダーシップのタイプがわかりスキル向上やリーダー育成にも活用されている理論
ヒートショック
急激な温度変化によって、血圧や脈拍が大きく変動すること。場合によっては心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こす。
非言語コミュニケーション
表情やジェスチャー、ボディランゲージ(姿勢、立ち方)などのコミュニケーション技法のこと
非侵襲的人工呼吸
口・鼻または鼻をマスクで覆い、空気を送り込む人工呼吸療法
ビタミン
微量でも体の働きを助ける栄養素。体内でエネルギーを効率よく使うのに必要な補酵素として働く。脂溶性と水溶性のビタミンがある。
ビタミンA
脂溶性ビタミンの1つで、視覚作用や発育、粘膜の維持などの働きを持つ
ビタミンB1
糖質の代謝を助け、神経や筋肉の働きを正常に保つ水溶性ビタミン。
ビタミンD
脂溶性ビタミンの1つであり、カルシウムの吸収、骨の形成などの働きを持つ
ビタミンK
血液の凝固に関与し、骨の健康にも関係するビタミン。不足すると出血が止まりにくくなる。
PDCAサイクル
計画、実行、評価、改善を元に、ある業務における継続的な管理をしていく手法
ヒドロキシアパタイト(リン酸カルシウム)
骨の硬さと強度に関与
ひもときシート
介護・福祉の現場で、利用者の行動や背景を多面的に理解し、適切な支援につなげるための分析ツール。評価的理解、分析的理解と共感的理解の3つの思考過程がある。
ヒヤリハット
過失はあったが、事故にならなかったもの
病院
医師や歯科医師が、公衆や多数の人々を対象に医療行為を行い、20人以上の患者を入院させることができる施設
病識低下
精神疾患や脳の損傷などによって、自分の病気や状態を適切に理解できない状態
標準予防策(スタンダードプリコーション)
感染症の有無に関わらず、すべての人に対して適用される感染予防の基本的な方法。例えば、手指衛生(手洗い)や個人防護具(PPE)の使用、器具や環境の清掃と消毒、呼吸衛生/咳エチケットなどがある。
開かれた質問
自由に答えられるような質問のこと。主な特徴として、相手の思いや考えを聞けたり、会話の内容を深めることができるなどがある。例えば、「午後はどのように過ごしますか?」。
貧困妄想
うつ病や統合失調症で見られることが多く、実際は違うのにお金がない、借金があるなどと思い込む妄想
ファシリテーション
会議において、合理的な結論を得るために効率的に参加者の合意形成を図る技術
FAST(Functional Assessment Staging)
認知症の評価スケールのうち、観察式でアルツハイマー型認知症の重症度判定に使われる評価スケール
フォーマルサービス(公的サービス)
国や地方公共団体などの公共機関や専門職が公的な制度に基づいたサービスや支援のこと。介護保険や介護支援専門員、社会福祉法人、民間非営利法人(NPO)行政、などがあてはまる。
フォロワーシップ
チーム内での働きにおいて、メンバーが主体的にリーダーをサポートする役割
不穏
落ち着きがない、叫んだり過剰な動きが見られたりと普段と違い穏やかでない状態を
不感蒸泄
気道や皮膚表面から自然に放出される水分のこと
腹圧性尿失禁
女性に多く、くしゃみや重いものを持ち上げる時など腹圧が上昇することで尿漏れが生じる特徴を持つ尿失禁
腹腔内
体内の横隔膜の下にある空間、胃、小腸、大腸、肝臓、腎臓などがある。
福祉三法
児童福祉法と身体障害者福祉法と生活保護法の3つが含まれる
福祉事務所
生活に困窮する人や福祉的支援が必要な人に対して、生活保護などの援助を行う行政機関。主な役割として、生活保護の実施、福祉サービスの相談、支援・地域福祉の推進などがある。
福祉避難所
災害対策基本法に基づいて運営され、災害時に特別な配慮が必要な高齢者や障害者が避難するための場所
福祉用具
介護や介助が必要な人の日常生活やリハビリをサポートするための用具や機器
福祉用具専門相談員
福祉用具の選定や使用方法の助言などを通して、利用者の自立の手助けや生活の質の向上、介護者の負担軽減を図る役割がある専門職
普通徴収
介護保険制度の第1号被保険者のうち、年金額が年額18万円以上の場合の徴収方法
プッシュアップ
脊髄損傷患者が習得する動作の1つとしても知られる、移乗や移動、褥瘡予防などを目的とし、座位の状態で上肢を使って臀部を座面から浮かす動作
不定愁訴
倦怠感や不眠、頭痛など何となく体調が優れない自覚症状があるが原因が分からない状態
不眠症
眠る環境が整っていても「眠れない・途中で起きる」などの状態が続き、日中の生活に支障が出ること。4大症状として、入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害がある。
フリーラジカル説
身体内で発生する活性酸素などのフリーラジカルが細胞や組織を傷つけ、その蓄積が老化の主な原因となるという理論
ブリストル便性状スケール
便の形状と硬さを客観的に分かりやすく分類するための尺度
浮力作用
身体に生じる浮力のこと。水中では体重が軽く感じられ、関節への負担が減って動きやすくなり、リラックスしやすくなるなどの効果がある。
フレイル
虚弱ともいい、年齢とともに心身が衰えていく状態
ブレインストーミング
例えばケアカンファレンスの場において、内容よりかは多くの意見を集めることに重きを置く手法
プレパレーション(心理的準備)
例えば子供への喀痰吸引の実施について、子どもがわかりやすいような声掛けや方法で処置の説明を行い、恐怖感や不安感を和らげるための考え
フロイト(Freud, S.)
精神分析学を創始し、無意識の働きを解明したオーストリアの精神科医。
プロダクティブ・エイジング
高齢者が健康で充実した生活を送りながら、経験を活かして社会に貢献し続ける生き方。有償労働、ボランティア活動、子どもの世話や親の介護、趣味など。
フローレンス・ナイチンゲール
イギリスの看護婦で、看護学の創始者と呼ばれ、「Notes On Nursing(看護覚え書)」を著した人物
分散的注意
複数の対象に注意を分散すること
ペアレントメンター
自身も障害のある子どもを持つ親であることが多く、同じ立場の経験者として、悩みや不安に寄り添いながら主に障害のある子どもを持つ親を支援するメンター(助言者)のこと
平滑筋
胃、腸、膀胱、血管など、内臓や血管の壁にある不随意筋
平均寿命
生まれたばかりの人が、その後何歳まで生きると予測されるかを示した平均年齢のこと
平均余命
ある年齢に達した人が、その後何年生きられるかを統計的に示したもの
ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など
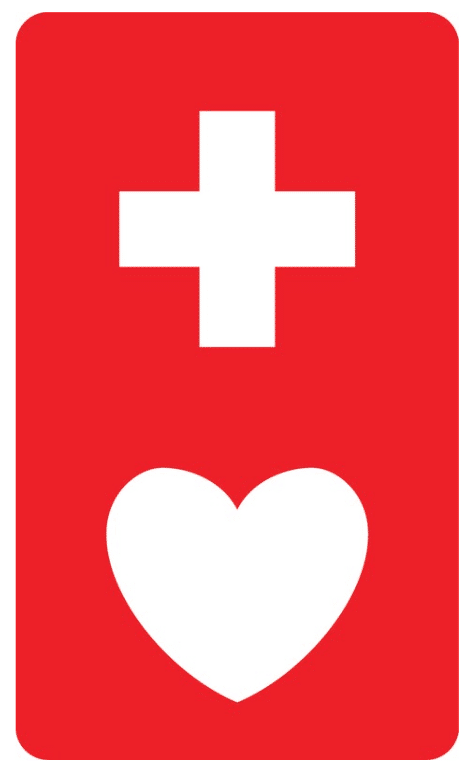
ヘレン・ケラー(Keller, H.)
視覚と聴覚に障害を持ちながらも教育を受け、障害者の権利擁護に尽力した社会活動家。
変形性膝関節症
膝関節の軟骨が変性や損傷によって、関節の痛みや機能障害が生じる疾患のこと。膝関節の痛みや腫れ、運動制限などの症状がある。
変性
正常だった細胞や組織の構造や働きが異常な状態に変わること
扁桃体
大脳の側頭葉にある神経核で、感情(特に恐怖や不安)の処理、記憶、情動反応の調節に関与する脳の構造のこと。
ベンクト・ニィリエ
スウェーデン出身であり、ノーマライゼーションの8つの原理を提唱した人物
便秘
排便の回数や量が減少し、便が出にくくなる状態のこと
法定後見制度
家庭裁判所が本人の判断能力に応じて後見人等を選任し、保護・支援を行う制度。後見・保佐・補助の3類型がある。
保健師
地域社会の健康増進を目的とし、住民の健康管理や疾病予防、健康教育を行い、保健活動を通じて地域の健康課題を解決する役割を持つ専門職
保健所
例えば、結核のような感染症患者に対する家庭訪問指導や、医療費の公費負担申請などを行う地域における公衆衛生の管理や感染症対策を担う重要な機関
ボディメカニクス
身体介助を行う際に「安全かつ効率よく身体を動かすための基本原則」のこと。1支持基底面を広くとる、2重心を低くする、3物や相手に近づく(重心を近づける)、4身体の大きな筋肉(大筋群)を使う、5ねじらずに身体全体で動く(体の軸を回す)、6動作はゆっくり・スムーズに行う、7押す動作より引く動作を活用する、8テコの原理やトルクの原理を活用する。
骨
骨の構造として、外側には骨外膜(骨膜)が覆っており、中心に骨質がある。骨質には、緻密骨や海綿骨が存在しており、その海綿骨には主に赤色骨髄や黄色骨髄などの骨髄がある。
ホメオスタシス(恒常性)
外界がたえず変化していたとしても、体内の状態(体温・血液量・血液成分など)を一定に維持できる能力のこと
ま〜も
末梢神経
脳や脊髄などの中枢神経以外の運動神経や感覚神経、自律神経をさす。
まつり縫い
裾上げやカーテンの仕上げなど、表に縫い目が目立たないようにする手縫いの手法
マルサス
イギリスの経済学者であり、『人口論』で貧困の原因を人口増加と資源不足に求めた経済学者。
慢性硬膜下血腫
主に頭部外傷によって、脳と硬膜(脳を覆う膜)の間の硬膜下腔に血液が溜まる状態の疾患
ミトコンドリア
細胞が活動に必要なエネルギー源であるATP(アデノシン三リン酸)を合成する細胞小器官
看取り期
利用者や患者が終末期に入り、生命の最終段階にある時期
見守り的援助
自立支援、 ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等のこと。
ミラーリング
相手の動作や表情をさりげなく模倣し、無意識のうちに親近感や安心感を生む関係構築の技法
ミルトン・メイヤロフ
「ケアリング」の概念を提唱した心理学者で、『ケアの本質』などの著書でケアの哲学を示した人物。
民生委員
地域住民の生活向上を目指し、地域の住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めるボランティアのことを何というか?
明確化(クラリフィケーション)
あいまいな話を、「つまりこういうことですか?」と整理して聞き返すこと。
明順応
眼の働きとして、眩しさになれる順応
無動
動き出せなくなること。パーキンソン病4大症状の1つでもある。
メタボリックシンドローム
肥満や高血圧、高血糖、高脂血症など、複数の生活習慣病のリスク要因が同時に現れる状態
滅菌
すべての微生物を死滅させることもしくは除去すること。高圧蒸気滅菌、放射線滅菌、 乾熱滅菌などがある。
メラトニン
睡眠に関わるホルモンであり、脳の松果体で生合成されるホルモン
申し送り
勤務交代時に前の勤務者が次の勤務者に、利用者の重要な情報を引き継ぐコミュニケーションのプロセスのこと。主な目的として、ケアの継続性を保つ、重要情報の共有、リスク管理がある。
網膜色素変性症
夜盲から始まり、視野狭窄や視力低下などがみられる疾患
燃え尽き症候群(バーンアウト)
仕事や役割に対する長期間のストレスや過負荷により引き起こされる、極度の肉体的および精神的疲労の状態。症状として、無気力や自己効力感の減少、仕事への無関心などがある。
モニタリング
日々の支援が計画通りか、支援方法はどうか、介護目標の達成度はどうかなどを判定すること
もの盗られ妄想
被害妄想の1つであり、実際には物が失われていないのに、自分の持ち物が他人に盗まれたと強く思い込む妄想
モルヒネ
医療用麻薬としても使われ、がんの痛みに対して鎮痛目的で用いることが多い麻薬
問題焦点型コーピング
ストレスの原因に直接働きかけて解決を図る対処方法
や〜よ
薬剤師
適切な薬物療法を提供する医薬品の専門家
役割葛藤
例えば、「仕事と介護の両立ができるか?」など、複数の役割に対して葛藤すること
役割取得
他の人の役割や期待などを自分に取り込んでその役割を実行すること
優生保護法
差別的な政策の一部として、後に改正された法律であり、1948年に制定され、出生前診断や不妊手術を通じて「優良な子孫の出生」を目的とした法律
ユニバーサルデザイン
年齢や障害にかかわらず、すべての人が使いやすい環境や製品をデザインすることを目指す概念
ユマニチュード
フランス語で「人間らしさ」といい、認知症の高齢者や介護が必要な人々に対して、人間らしい対応をすることで尊厳を守るケアの方法。見る、触れる、立つ、話すの4つの柱がある。出会いの準備、ケアの準備、知覚の連結、感情の固定、再会の約束の5つのステップがある。
養護老人ホーム
家庭環境や経済的理由により、自宅での生活が困難な高齢者が入所できる福祉施設。基本的には自立した高齢者が対象で、軽度の支援が必要な方に対して生活援助を提供する。
腰髄損傷
脊髄損傷の一種で、腰髄が損傷することで、対麻痺(下半身の麻痺)や膀胱直腸障害など、下肢の運動・感覚機能の障害が生じる状態。
腰部脊柱管狭窄症
腰椎にある脊柱管が何らかの原因で狭くなり、神経が圧迫され腰痛や下肢のしびれ・痛みを引き起こす疾患。主な症状として、腰痛、下肢の痺れや痛み、間欠性跛行などがある。
要約
相手の話の 重要なポイントを簡潔にまとめる技術。(「最近、疲れやすくて食欲もなくて、外に出るのも億劫で…。→「体調がすぐれず、外出も大変になっているんですね。」)
抑圧
適応機制の1つである、自分の感情等を無意識に押し込めてなかったことにする働き
抑うつ状態
長期間にわたって気分が低下した状態
欲求階層説
マズローが提唱した、人間の欲求を5つの段階に分け、どのようなきっかけ(欲求)で行動を起こすかをピラミッド状に表したもの。下から順に、生理的欲求、安全欲求、所属・愛情欲求、承認欲求、自己実現欲求とある。
4点杖(多点杖)
先端が4つに分かれて接地する支えがしっかりした安定性の高い杖のこと。バランスが不安定な人に適している。
ら〜ろ
ライチャードの老齢期の性格類型
老年期における人々の適応の仕方や性格特性を観察し、性格や生活態度をいくつかのタイプに分類した理論。適応型の円熟型・防衛型(装甲型)・依存型(安楽いす型)、不適応型の自責型(内罰型)・憤慨型(外罰型)の5つのタイプがある。
ライフレビュー
過去の思い出を振り返り、自分の人生を再評価することで、自己肯定感や充実感を得る心理ケアの手法
ラポール
援助者と利用者との信頼関係のこと
リアリティ・オリエンテーション (RO)
日付、時間、場所、天気などの現実の情報を繰り返し伝えることで、認知症の方に現実認識を促すケアの手法のこと
理学療法士
身体機能の回復や維持を支援し、基本動作の向上を目指すリハビリ専門職。主な役割として、基本的動作(立つ・座る・歩くなど)の維持・回復を目的としたリハビリを行う。
リッチモンド
『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』を著し、ケースワークの理論を築いた社会福祉の先駆者。
リハビリテーション
元の語源である「再び適したものにすること」である、全人間的復権を目的とした考え方。医学的、職業的、社会的、教育的の4つに分類できる。
リビングウィル(終末期医療における事前指示書)
終末期における医療上の処置や治療に関する希望や指示をあらかじめ意思表示した文書
リフレージング
相手の言葉を別の表現に言い換えて確認し、理解を深めて誤解を防ぐ共感的な対話技法
リフレーミング
物事の捉え方を変えて、新しい視点や枠組みから再度考え直すこと
リモデリング
骨は日々、骨芽細胞が新しい骨を作り、破骨細胞が古くなった骨を破壊し骨を維持している
流動性知能
60歳ごろから急激に低下する特徴があり、新しいことを学んだり覚えたりする知能のこと
利用者主体
利用者自身が自分の生活やケアに関して主体的に意思決定を行い、その人らしい生活を支援する考え方。基本理念として、尊厳の保持、自立支援、自己決定権の尊重がある。
良肢位
身体の動きが制限されたとしても、日常生活動作で支障の少ない姿勢のこと
療養介護
医療的ケアや常時の介護が必要な重度障害者を対象に、生活と医療を一体的に支援するサービス
リロケーションダメージ(移り住みの害)
施設への入居や人間関係の変化など、生活環境の変化によって、不安や孤独感、せん妄などの症状が見られること
リン
ミネラルの1つで硬組織の形成や酵素活性、血球機能の維持など
冷罨法
身体の特定部位を冷やして炎症や痛みを抑えるケア方法
レストレッグス症候群
下肢を中心にむずむず、かゆいといった不快感がおこる睡眠障害
レスパイトケア
介護をしている家族が一時的に介護を離れて心身の回復の時間を設けるための手段
レスポンデント条件付け
元々の刺激と新しい刺激が一緒に結びつくことで、新しい刺激だけでも反応が起こる条件付けのこと
レミニシング
過去の出来事や思い出を自然に振り返ること
レム睡眠
「浅い眠り」で、脳は活発に動いている状態。筋肉は弛緩して体は休んでいるが、眼球は動いており、夢を見るのはこの時間。記憶の整理・定着、感情の処理、脳のリフレッシュなどの役割を持つ。
老化
生理的老化と病的老化がある
老化プログラム説
人間の細胞は分裂回数が限られており、この限界を超えると細胞が老化を始めると提唱されている理論
老眼
眼について、加齢により近くのものが見えにくくなる状態のこと
労作性狭心症
狭心症のうち、運動など心臓に負荷がかかった時に症状が生じる種類を何というか?
老人性難聴
加齢によって内耳や聴覚中枢の機能が低下し耳が聞こえなくなる難聴。主な特徴として、感音性難聴であること、高音域の音が聞こえにくいなどがある。
老人福祉センター
高齢者が 交流や趣味活動を行うための地域施設。食事会や健康相談、レクリエーションなどが実施される。
老年期症候群
加齢による身体機能の全体的な低下が原因とする、高齢者に多く見られる健康問題が複数重なる状態
老齢年金
公的年金のうち、65歳以上の人に支給される年金のこと
老老介護
高齢者が高齢者を介護すること
ロバーツ
1970年代にアメリカで障害者の自立生活運動(IL運動)を展開する
ロフストランドクラッチ
手指や手首に支障があり、握りだけで身体を支えるのが難しい人が対象であり、握り部分と前腕の2点で体重を支える特徴をもつ杖

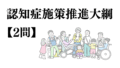
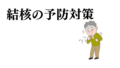
コメント