こんにちは、しょうです。
今回の問題を見ていきましょう!
問題1
問題43 次のうち,認知症(dementia)のリスクを高める要因として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 身体活動
2 不飽和脂肪酸の摂取
3 歯がなくなることによる咀嚼機能の低下
4 難聴による補聴器の使用
5 ボランティア活動引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験」
正解
◯3 歯がなくなることによる咀嚼機能の低下
解説
「◯3 歯がなくなることによる咀嚼機能の低下」がなぜリスク?
①咀嚼による脳への刺激が減少
→ 記憶や学習に関わる海馬の働きが低下
②柔らかい物中心の食事になりやすい
→ 栄養バランスが偏り、脳の健康に影響
↓
「口腔ケア」が重要となる
・歯を守る=脳を守る
・義歯の調整・歯科受診・毎日の歯みがき
・高齢者にも定期的な口腔チェックを
↓
噛む力を保つことは、認知症予防にもつながる
認知症(dementia)のリスクを高める要因
① 修正可能なリスク要因(予防可能)
・難聴
・うつ病
・社会的孤立
・高血圧・糖尿病
・運動不足
・咀嚼機能の低下 など
② 修正困難なリスク要因(変えられない)
・加齢
・遺伝(ApoE4等)
・性別(女性) など
③ その他 注目されるリスク要因
・睡眠障害
・頭部外傷 など
認知症の予防に向けてのアプローチ
・有酸素運動(週150分以上の中強度運動)
・野菜・魚中心の食事(地中海式食事など)
・定期的な健康診断と生活習慣病管理
・社会参加(地域活動、家族交流、ボランティアなど)
・趣味・読書・学習など知的活動
・良好な睡眠環境の確保
・口腔ケア(歯科受診、入れ歯の調整など)
介護現場で実践できる「認知症予防」の具体的な関わり方
①動く機会をつくる
例)散歩や体操の声かけ、車椅子に頼りすぎず自立を促す移動支援
②噛んで食べる
例)常食や刻み食の活用、「今日は○○ですね」と五感を刺激する会話
③口から健康を守る
例)入れ歯の清掃サポート、口腔内チェック、歯科往診の調整など
④人とつながる
例)グループ活動への誘導、声かけの工夫、1対1の会話の積極的実施
⑤脳をやわらかく刺激
例)昔話を引き出す会話、カレンダー活用、窓の外の景色に注目する声かけ
⑥生活リズムを整える
例)日中は活動的に、夜間は静かな照明・環境づくり、朝の日光浴の誘導
他の解説
×1 身体活動
↓
・認知症の予防につながる要因
・ウォーキングなどの有酸素運動は、脳血流を良くし、神経細胞の維持に役立つとされている
×2 不飽和脂肪酸の摂取
↓
オメガ3脂肪酸(DHAやEPA)などの不飽和脂肪酸は、神経細胞の機能維持や炎症の抑制に役立ち、認知症のリスクを低下させる
×4 難聴による補聴器の使用
↓
・難聴そのものは認知症リスクの一因だが、補聴器の使用はリスクを軽減する対策である
・音を聞くことで脳に刺激が伝わり、認知機能の低下を防ぐことが期待される
×5 ボランティア活動
↓
・社会参加の一種であり、人との交流や目的意識が認知症予防に有効
・孤立を防ぎ、心の健康にもよい影響を与える
問題2
問題81 認知症(dementia)の発症リスクを低減させる行動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 抗認知症薬を服用する。
2 睡眠時間を減らす。
3 集団での交流活動に参加する。
4 運動の機会を減らす。
5 飽和脂肪酸を多く含む食事を心がける。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第32回介護福祉士国家試験」
正解
3 集団での交流活動に参加する。
解説
「◯3 集団での交流活動に参加する。」が、なぜ認知症の発症リスクを低減させる行動になる?
①会話・人付き合いが脳への刺激に
→思考・記憶・判断などを使う機会が増える
②孤立やうつ状態の予防に効果的
→心の健康が守られることで、認知機能も維持しやすい
例)地域のサロン・ボランティア・趣味のグループ参加、デイサービスなどでのレクリエーションや集団体操、声かけの工夫、1対1の会話の積極的実施
↓
孤立を防ぎ、楽しく交流することが認知症の予防につながる
他の解説
×1 抗認知症薬を服用する。
↓
・予防ではなく治療のための薬であり、発症リスクの低下(予防)にはならない
・抗認知症薬(例:ドネペジルなど)は、すでに認知症を発症した人に処方され、進行を遅らせる目的で使われる
×2 睡眠時間を減らす。
↓
質の良い睡眠は、脳内の老廃物(アミロイドβ)を除去する働きがあるため、睡眠不足は認知症リスクを高めるとされている
×4 運動の機会を減らす。
↓
適度な運動(特に有酸素運動)は、脳の血流を良くし認知症の予防に効果がある
×5 飽和脂肪酸を多く含む食事を心がける。
↓
・飽和脂肪酸(バター、脂身の多い肉、加工食品など)の過剰摂取は、動脈硬化や脳血管障害のリスクを高め、認知症のリスク因子となる
・オリーブオイル、魚やナッツに含まれる不飽和脂肪酸(オメガ3など)などは、認知症予防に有効とされている
おわりに
今回は以上です。次回もお楽しみに!
特定の内容のまとめを作って欲しい、この問題の解説をしてほしい、などご要望等あればぜひコメント等書いていただけると、今後のコンテンツ作成の参考になりますのでぜひお待ちしております。
また、YouTubeでの動画形式での過去問解説やKindleでオリジナルの模試や一問一答の問題も作成しているので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください!


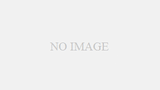
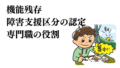
コメント