こんにちは、しょうです。
今回の問題を見ていきましょう!
問題
問題63 Aさん(80歳,女性)は,脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症で左片麻痺があり,介護老人保健施設に入所して在宅復帰に向けた訓練をしている。嚥下障害もあるため,経鼻経管栄養による栄養摂取をしているが,経口摂取できないことでイライラしてチューブを抜去したことがある。医師からは一時的な治療であると説明を受けて同意していた。
経管栄養中に介護福祉士が訪室すると,チューブを触りながら,「自分の口から食べたいから,このチューブを抜いてほしい。見た目も良くない」と訴えがあった。看護師に連絡し,チューブが抜けていないことを確認してもらった。
このときのAさんへの介護福祉士の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 チューブを抜かないようにAさんの右手を固定する。
2 経管栄養が早く終わるように滴下速度を調節する。
3 医師や看護師にAさんの思いを伝える。
4 Aさんに胃ろうの造設を提案する。
5 Aさんに経口摂取を提案する。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験問題63」
正解
3 医師や看護師にAさんの思いを伝える
解説
Aさんについて
・経口摂取できないことでイライラしてチューブを抜去したことがある。
・「自分の口から食べたいから,このチューブを抜いてほしい。見た目も良くない」と訴え
↓
Aさんへの介護福祉士の対応としてどうすればよい?
「3 医師や看護師にAさんの思いを伝える。」が正解
・本人の意思を尊重し、気持ちを受け止める
・医療職と連携し、安全かつ適切な支援につなげるはたらきをする
↓
本人の思いや希望を代弁し、必要な支援につなげる働きかけ、本人の権利や声を守る行動といえる(=アドボカシーの実践)
アドボカシーとは?
本人の権利や意思を代弁し、必要な支援(制度や医療)につなぐ行動
介護や福祉の現場では…
・自分の気持ちや希望を伝えることが難しい人
・支援が必要なのに適切に届かない人 など
↓
こういった方々を支えるための1つの行動としてアドボカシーがある
他の解説
×1 チューブを抜かないようにAさんの右手を固定する。
↓
・手を固定することは身体拘束となり、原則認められない
・本人の思いを尊重し、話し合いやケアの工夫で対応することが優先される
×2 経管栄養が早く終わるように滴下速度を調節する。
↓
・滴下速度の調節は医療行為であり、介護福祉士が行うことはできない
・落とす速度を勝手に変えると吐き気や下痢、誤嚥のリスクがある
×4 Aさんに胃ろうの造設を提案する。
↓
・胃ろうの造設は医師の判断と家族・本人との話し合いで決めるものであり、介護福祉士が提案することではない
・今回は一時的な経鼻経管栄養で対応しているため、胃ろうの提案は時期尚早である
×5 Aさんに経口摂取を提案する。
↓
・嚥下障害があるため、経口摂取の可否は医師や専門職が判断するべきである
・勝手に経口摂取を勧めると誤嚥や窒息の危険がある
おわりに
今回は以上です。次回もお楽しみに!
特定の内容のまとめを作って欲しい、この問題の解説をしてほしい、などご要望等あればぜひコメント等書いていただけると、今後のコンテンツ作成の参考になりますのでぜひお待ちしております。
また、YouTubeでの動画形式での過去問解説やKindleでオリジナルの模試や一問一答の問題も作成しているので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください!

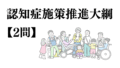
コメント